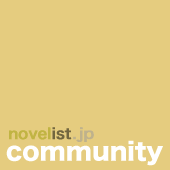バトンを繋ごうRPG 『勇者の旅立ち』[小説コミュニティ]
勇者ノベリットの冒険
| かざぐるま} かざぐるま |
勇者は村を出た。装備も魔法もまだ持っていない。とりあえず北の森に向かってノベリットは歩き出した。そこに突然!! |
2013-07-11 19:30:04 |
|
コメント (203)
 匿川 名 2019-07-28 21:30
匿川 名 2019-07-28 21:30
落ちよ、落ちよ、墜ちよ。
男は水晶球の上にひらひらと、両の手を枯れた蝶のようにかざしながら、恍惚の呪詛をただ述べ続けた。
その中に映るのは黒く閉じた球だった。
塵のように薄く粉舞うそれは、カイザーとアニエスを内に閉じ込める胎そのものだった。
はあはあと息遣いも荒く、男はぎらぎらと怪しく刮目したままで呪いの完成を待っていた。
落ちよ、落ちよ、墜ちて焦がせよ。
男の邪悪な祈りに応じて黒雲が空に舞う。
蛇蝎のような『それ』は、或いは凶兆の竜のように天空を舞い、命在る魔のように地上の球を、或いは黒き胎を睨めつけるかのようだった。
その竜の体躯に白い鱗の模様が這う。
空に低く轟く地響きのようなそれは、男が編む邪心の拳で、
詰まりは、
雷の姿をしていた。
 匿川 名 2019-07-28 21:18
匿川 名 2019-07-28 21:18
※業務連絡※
さて、プロフで何となく告知したとおり、今日はこれから『リアルタイム更新』で行きたいと思います。
脇にはサーモスのタンブラーに入った冷えたビールが一杯。
手元のMacBookAirのバッテリーは92%。
目標は午後11時半頃までで行こうかなあと。
いま、ぐびりと1口。
誰も見ていないでしょうけど・・・では、書き始めますね。
 匿川 名 2019-07-15 23:52
匿川 名 2019-07-15 23:52
※
闇は濃く二人を包んだ。
カイザーとアニエスにはもう殆ど視界は無い。
取り囲み在るのは百万の黒犬の牙と、そこからだらだらとしたたる汚らしく臭い獣の涎ばかりだ。
牙は噛まず、威嚇を繰り返す。
アニエスが白刃で薙いでも黒い霧と化してはまた闇に戻り、汚い牙へと還る。
カイザーは猛烈に殴りつけるが粉砕しても同じことだった。
手応えはある。粉砕はされる。
しかし無数の牙は闇へと戻り、牙へと還る。
無限の闇が二人を包囲しつつあり、通常、そこには絶望しか無いと思われた。
だが――――
「カイザー、何を嗤うのです」
アニエスがカイザーに尋ねた。
邪悪な闇の中ですら、カイザーの朗らかな微笑みはその気配をアニエスに雄弁に伝えた。
「なに、ここまでやり込められたのは初めてのことではないかと思っていたのよ。実に八方塞がり、そのように見えるのだろうな」
鷹揚とした言葉の紡ぎにアニエスもつられてふふと微笑む。
「まるで他人事のようですね」
そしてそう呟くと、カイザーははっはと嗤い声を上げた。
「今、間違いなく我らの様子を見ている者が居る。絶対安全な処(ところ)から、我への妬みだけに狂い、対し震えることさえ出来ない哀れな小男がな。――――そう、我が嗤いを堪えきれないのは、当(まさ)にこれが『他人事』だからよ。覗く世界に、完成を夢見たとして――――嘆くが良い。何しろ我らには『英雄』がいる。今の危難など直に消し飛ぶのさ」
二人を取り巻く闇はいよいよその濃さを極め、アニエスは束の間カイザーの方を首だけ回して垣間見た。
するとカイザーも同じようにアニエスの方を眺めていた。
彫像のように彫りの深い男の顔が、それまで彼女が見たことも無いような慈愛を湛えて向けられていた。
瞬間、その瞳の中に吸い込まれそうな何かをアニエスが感じたまさにその時、
「ところでお前――――いい女だな」
朴訥とした口調でカイザーがそう呟いた。
アニエスの口元が緩み微笑みを形作ると同時に、
歪な球のような形をした闇は、
――――二人を、その胎に完全に飲み込んだ。
 匿川 名 2019-07-15 23:47
匿川 名 2019-07-15 23:47
その唸りは物言わぬ剣の訴えのようで、応じて黒い石を受け取ったノベリットは、左手に石を持ち替えると、ゆっくりと右手で柄を握り鞘から剣を抜いた。
鈍い黄金色をした柄にはふわりと血の赤をした文字が薄ら輝きながら浮かび上がる。
『掲げて撫でよ』
そこにはひと言、そう綴られていた。
掲げて、撫でよ。
ノベリットは言葉を受けて、眉を潜めながら左手の中に包み込まれた黒い石を刃へと向けた。
吸い込まれるように、研がれたままのような白銀の刃へと、漆黒の色をした石が近づいていく――――。
 匿川 名 2019-07-08 00:04
匿川 名 2019-07-08 00:04
ふとその種田の落ち着いた様子から、ノベリットは自身の濡らした股間のことが思い出され、不意に湧き上がった恥ずかしさにぐうっと深く俯いた。
「気にすることはありません。私だって怖い。自然なことだと思いますよ。むしろ、彼らが異常なだけです」
種田はそう呟いて顎で軽くカイザー達の方をしゃくり示した。
「じゃあ、じゃあなんであなたは」
ノベリットは尋ねるつもりだった。
種田のそのどこか超然とした在り方を。
何故そう在れるのか。
無限に湧き上がる恐怖をどうやって飼い慣らしているのか。
その時種田が懐に手を入れて、ごそ、と何かを取り出した。
「これを使いなさい」
種田はそしてそう呟き、ノベリットにひとつかみの平たく黒い石を差し伸べた。
「これは」
尋ねるノベリットに種田は頷いた。
「あなたがきっと探していたものだ。そして僕が父から預かってきたものでもある。これは古代語で『ジャクワィ・デゥ・トルディステゥーン』というもので、今の言葉で言うならば――――『伝説の砥石』だ」
ノベリットは目を見開いた。
「世界が終わろうとしていることは父も識っていた。
我らの祖先の霊が囁いたらしい。
だからこそ私はあなたを追ってきた。
これを、いまこそその手に取って――――」
呆然とノベリットは種田が差し出す黒い石に向け、自らの右手の平を被せるように伸ばし始めた。
その時、ノベリットの腰で伝説の剣か小さく震えるような唸りを上げ始めた。
 匿川 名 2019-07-08 00:01
匿川 名 2019-07-08 00:01
「やあ、これは酷い」
ふと、ノベリットの右耳の側からそっとそんな声が響いた。
あまりにその距離が近かったので、反射的にノベリットは首を勢いよく回し声のした方に振り向いた。
そこに立て膝で腰を下ろしていたのは一人の男で、視線は黒龍のような渦巻く黒雲とその直下において宙(そら)を見上げる男と女――――カイザーとアニエス――――の方に向けられていたままだった。
「――――種田――――さん」
ノベリットは呆然と男の名前を呼んだ。
男は、種田和夫は口元に微笑を浮かべてノベリットの方に少し顔を向けると軽く会釈をした。
「しばらくです」
種田はそう言ってまたノベリットから視線を切り、前方に広がる禍々しいばかりの光景を眺めた。
『禍々しい』
実に、禍々しい。
なのに、とノベリットは思う。
なのに、なぜ種田さんはこんなに涼しい顔をしている?
 匿川 名 2019-07-03 23:02
匿川 名 2019-07-03 23:02
「拙いなこれは」
カイザーがそうぼそりと呟いた。
目を細め、アニエスが取り囲む闇に向け刃を横薙ぎに一閃させた。
しかしまさに虚空を切るが如く、刃は何の手応えも無いままに水平の円弧を描くのみだった。
「何が起ころうとしているんです」
アニエスはカイザーに尋ねた。
「なに、我らを灼こうとしておるのだろうよ、あの阿呆は。此処は焦点で中点と為るのだ――――おそらく、雷のな」
その言を受けてアニエスは濃く満ち行く闇の中に向け、一歩足を踏み出した。
すると忽ち――――
――――狗が闇の中から首をもたげ、滴る涎に汚れた牙をアニエスに向け突き出してきたので、反射的に彼女は身をよじりそれを避けた。
そしてそのままの姿勢からさらに垂直に刃を薙ぐ。
闇の中から実体化した犬の首は彼女の白刃に打ち落とされて、どたっと地面に転がった。
かと思うとそのまま闇が伸び、落ちた首と自らを繋ぎ、拾われた首はしゅうと音を立てながら霧の粒子と為って闇の中へとまた消えた。
※
地面に膝をついたまま、ノベリットはがくがくと腿が震えるのを止める術も無く、閉じ行く闇をひたすらに呆けのように眺めていた。
その時ふと内腿に温い何かを感じて俯いた。
――――下衣がぐっしょりと湿っている。
自分が失禁していたということにすら気づかず、いや、気づかなかったことが急に愉快に感じられでもしたのか、ノベリットの両足から力が完全に抜けた。
くたっと膝が折れ、地面にぺたりと尻餅をついた。
がくんと落ちた両腕で身体を辛うじて支えると、世界の総てが邪悪な観劇のように感じられた。
その彼の耳に届いたのは地響きに似た低い、うねりの音だった。
――――それは遠雷。
空にぼんやりと向けた彼の目の中に、渦を巻くように黒雲が立ち上るのが映った。
蜷局巻く竜のように、渦の中点は目指している。
打ち下ろす拳の先を見据えている。
球のように閉じ行く闇の直中を、
『いざ、いざこそ皇を討たん』と喜悦に満ちた狂った目が、
ひひと歪んでのたうっているかのように――――
 匿川 名 2019-06-06 22:49
匿川 名 2019-06-06 22:49
揺らぐ、
陽炎のように、
頼りなく吹けば消えるかのように、
『ゆらあ』と揺らぎ、それでも白刃を薙ぐ。
「カイザー」
とアニエスは背中を預ける男の名を呼んだ。
「応(おう)」とカイザーが気安く、実に気安く応じる。
旧知の友人から『煙草が切れたので一本くれ』と頼まれでもしたかのような、底抜けの気安さだ。
例えばそれまでの智を総動員してなお説明のつかない事象を、ヒトは奇跡と呼ぶ。
或いは魔法と、或いは祝いと、或いは呪いとこそ、呼ぶ。
世界の総てが己達に呪詛を向ける瞬間を前にして、正気を保つことは難しかろう。
だからこそ討たれ伏して動かぬ少女二人は――――喩えいま、死の川を渡ろうとしていたとしても――――『絶望と合い面することが最早無い分』だけ、この場においては幸せであるとすら言えるのかも知れなかった。
だが、
緑の闇の中から一際濃い『滾り』がくねり、ひゅっと音も無くアニエスを襲った。
反射的に身を翻したアニエスは『滾り』の奥の汚れた白を刃で打ち逸らす。
そこには『狼の牙』があった。
上目に睨み付けると、牙の先に伸びる緑の煙で形作られた曖昧な狼が後ろに飛び戻りふわっと虚空に消えた。
ふふっと鼻から抜けるような微笑みがアニエスの耳を打った。
それに導かれるように、視線は目前の敵から微塵も動かさず、気配だけを背後に送る。
「豪胆とは云わぬよ。足が震えている。だがそれでも主(ぬし)は『ひとかどの剣士』なのだな」
深く落ち着き払った青銅のような声音がアニエスの耳をまた打つ。
「――――恐縮至極」
アニエスが微笑みながらそう呟いた。
それまで信じていた世界の総てが敵に成ったように見えたその瞬間でさえ、
剣士はそのとき、間違いなく皇とともにそこに在った。
しかし緑の闇はふたりを完全に包み込み、
怒濤の如く押し潰さんばかりに、
『ぐうっ』と殆ど音を立てるかのように、
二人を極として、
点を結ぶかのように、
そこで閉じようかとでもするように、
『勇者』の見る前で、
内に向けて『収約』を始めていった。
 匿川 名 2019-06-02 23:50
匿川 名 2019-06-02 23:50
※閑話休題※
わあ、なんだかにわかにダークファンタジーっぽい!
・・・ような気がします(爆
しかしこの展開でノベリット大丈夫なのかなあ?
一応主人公なのに情けないぞ!
アニエスとカイザーだけ戦わせて良いのか?!
『緑の閃光』に貫かれた『なんちゃって二人っ子』のマナとカナのその後は一体?!?!?!
・・・まあ、懲りずに続けますが、実は脱線・超・上等です!
どなたでもテキトーに流れを変えていただければ私としては乗っかりますが、さて?
 匿川 名 2019-06-02 23:44
匿川 名 2019-06-02 23:44
その歪んだ頬の肉が引きつるようにたわむのを、ヒトは『喜悦』と判じるのだろう。
「かかっ」と金属質な音が漏れたのはその口の中からであって、ヒトはそれを『法悦』と呼ぶのであろう。
世界を『紡ぐ』のは何であるのか。
その問いに立ち返るなら、『人』と答えるべきなのだろう。
あらゆる命に意思があるなら、あるいは、
あらゆる存在に意思があるなら、
その観測する数多の事象は、ただそこに在るだけなのに、意味を見出そうとするものは、万物において『人』のみに過ぎないからだ。
―――ならば、
世界を詠むものは何であろう。
眺め慮り、在る姿からその様(ざま)を心に詠むものは、何であろう。
皇よ、
皇よ、
わが、皇よ!
――――我は汝の屍を踏み越えることで世界の頂に至らんとする者為り――――
歪んだ男は歪んだ微笑みをその貌(かお)に貼り付けたまま、ゆらゆらと両の掌を水晶球の上に揺らした。
我は我こそは――――世界を詠む者為り。
そして、その透き通る玉の中に、
その玉に満ち行く緑色をした虚空の中に、
男は骨張ったひょろ長い人差し指を呪いを込めるように向けた。
邪悪な玉の中にたちまち垂れ込めるような灰色をした暗雲が立ち昇る。
それは此処とは異なる場所で、世界を占める空の色。
ひひっ、と男が嗤う。
邪悪が満ちる水晶玉の中で、独り輝きを遺しつつ抗う屈強な男の頭上に、酷く邪悪な意思を持った暗雲が満ち満ちる。
――――雷が落ちようと、している。