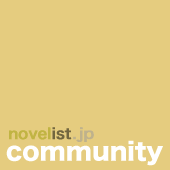バトンを繋ごうRPG 『勇者の旅立ち』[小説コミュニティ]
勇者ノベリットの冒険
| かざぐるま} かざぐるま |
勇者は村を出た。装備も魔法もまだ持っていない。とりあえず北の森に向かってノベリットは歩き出した。そこに突然!! |
2013-07-11 19:30:04 |
|
コメント (199)
 匿川 名 2025-06-28 09:49
匿川 名 2025-06-28 09:49
どうも、匿川です。
はい、生きてます(爆
やっちゃいました、半年放置!
やったことは無いんですがスマホゲーの『放置系』っていうのはこういう感じなんでしょうか(←絶対違う
次はもう少し早めに書きます。
私以外に全国にもう一人くらい読んでくれていると・・・良いなあ。
あと、バトンを繋ぎたいです。
単独走者になって長いもので、ちょっと切ない・・・。
お笑いでもホラーでも、感動系でもシュール系でも。
改変、設定キャンセル等全く問題なしです。
私は能力的にはアレですが、繋げていただければ全力で打ち返させていただきます。
そう、テニスで言うところのラリーがしたい!
でもえっちなのは書けませんのでその点だけは平にご容赦を(滝汗
かざぐるまさんも不在になって長いですし、正直あんまり期待はしていませんけど・・・
希望を持って、夢を見るくらい・・・良いんじゃないかな、と。
 匿川 名 2025-06-28 09:41
匿川 名 2025-06-28 09:41
――暗がりで目が覚めた。
いや、自分は目が――覚めているのか?
瞼を開いている感覚はある。
否、『開いている』と自分は知覚する。
だが、それが真実開かれているのかは、実は知りようが無い。
なぜなら――試しにと閉じてみた両の瞼は、等しく変わらぬ風景――つまりは、果てなく底無く、とこしえとも言える深淵に渉る暗闇を、ただそこに広げたのみであるからだ。
ならば、と私は改めて目を閉じる。
もしかするとと考える。
私は目を、光をこそ、失ったのかも知れない。
それは嘗て子供の頃偶然に想像し、ぞっと肝を冷やした想像の仮定。
そして今私を覆うのは、不意に実現したその仮定が覆い尽くす私の世界。
なのに、私は――
不思議なほど、落ち着いている。
それは、現実感が伴わないからだろうか。
突然の暗闇の訪れに、神経が麻痺して理解が追いつかないのだろうか。
急激に激しい痛みに襲われた身体は時に痛覚を拒否する。
事故で手に湯を被せたとき、料理の最中に手を少し切ったとき。
一瞬のひやりという痛みのあとにやって来たのは冷たい現実認識で、多少のひりひりする感覚はあれどもそれは決して破滅的では無く。
そんなことを思っていたときに――
――不意に指先に何かが触れたので、びくりと身を竦めた。
それは不思議なほど温く、この世のものとも思えないような優しさを湛えており、
瞬間――それが誰かの指先であると、完全に理解した。
懐かしいその感触はそちらも逆にびくりと竦み、続いて自分と全く同じように緩んだ。
それが誰の指先であるかは、明々白々だ。
幼い頃から慣れ親しんでいるので、そのわずかなばかりの感触でも間違えることは無い。
「マナ」
――と、その指先の持ち主に対し、
カナは囁くような声で小さく、
応えを求め、頼りなく呼びかけた。
 匿川 名 2024-12-29 22:41
匿川 名 2024-12-29 22:41
『途(みち)を繋ぐ』とは。
何者が征くための行路を何者かが繋ぐことを、その為の行為と過程を指すとするのなら。
我が為そうとすることは、まさにその『途を繋ぐ』行為に相違ない。
『世を統(す)べるとは』
数多の世界を全て統べることを意味するのなら。
我が為そうとすることは、まさにその『世を統べる』行為であるのに相違ない。
――為れば、だからこそ。
『黒の魔法使い』は皺枯れた両の手を伸ばし、眼前の水晶球を掴み取り、
足下に出来うる全ての腕力を用い、――叩き付けた。
がしゃ、というその透明さとは似つかわしくないくぐもった音とともに、呆気ないほど簡単に、玉は砕けた。
其れが四散八散する前に、微かな束の間にも満たない一瞬に、
『犬』の横顔がそこに見えた気がして、
魔法使いは思わず反射的にその目を背け、顔を衣で覆いかけた。
しかし、その次のひとときには、
足下に砕けるのはモノとしての意味を為さなくなった水晶の破片、破片、破片に過ぎなかった。
ぐいと魔法使いは顔を上げた。
眼の前に広がる光景――。
魔法使いは其れを意図していた。
そしてその通りのモノが眼前に広がるのを観て――
魔法使いは笑みを浮かべた。
其れは愉悦そのものといった趣(おもむき)で、
「かはッ」
思わず、その口から漏れ出たのはそんな簡単の短い気配だった。
魔法使いの目の前には、横向きに、水平に、
『線』が走っていた。
揺らぐきらめくその線は不穏で、不遜で、
鈍く煌(きら)めきつつ、ぎらぎらとヒトを惹く妖しさに満ち、
恰(あたか)も『世界を統べる窓』であるかのように、ゆらゆらと上下しつつ、
とこしえの闇にも似た、深く昏い安らぎにも似た、
――無限の深淵をその切れ目の中に、豊かなばかりに湛えていた。
 匿川 名 2024-09-01 10:24
匿川 名 2024-09-01 10:24
『わあ、月イチ連載だ!』とか言った直後に気がつけば3ヶ月以上間隔が開いている罠(汗
大作系の漫画家さんでは時々ある現象なんでしょうけど、アマチュア作家でこれをやっちゃいけない気がする(滝汗
でも久しぶりに筆を執ってみるとそれなりに書けたので良しとします。
マナとカナの経過も書かなきゃいけないと思いつつ、ノートPCをを新調したので辞書ファイルがまっさらなんですよ。
だから変換がなかなか思い通りに行かずに『うーん』と思っています。
結局使い慣れないとどうにもならないんでしょうけどね。
『全国に3人くらいいると良いなあ』と思うこの物語の読者様のために、今後はもう少し頑張って書くようにしたいです。
・・・いや・・・そんなにいるのか?(←不安
 匿川 名 2024-09-01 10:17
匿川 名 2024-09-01 10:17
「やれやれ、やっと来たのね。遅かったじゃない」
そして老婆はそう呟いた。
ノベリットは一度頷くと、
「すまない、ヴァンダール。途(みち)が分からなかった。つい先程までは」
と老婆に告げ、軽く頭を下げた。
その様子に老婆――ヴァンダール――はふふっと口元を歪めて微笑んだ。
「まあ、仕方ない。『夢に届くのはそれを信じる者のみ』だからねえ。でも、大したもんだ」
「何がだ」
「あんたは『自分の夢』の中に他の『意識』を、『ニンゲン』をそのまんま連れてきたんだよ?
どれだけの『想いの強さ』があればそんな半ば『宇宙を超えるようなこと』が出来るのか、私にはさっぱり分からないけど、でもひとつだけ言える。
それは――『あんたならそれは可能だと、私は信じていた』ということさ」
そう言うとヴァンダールは安楽椅子から大儀そうに立ち上がり、小屋の窓辺へ向かって歩いた。
そして窓の外をそっと指さす。
仲間とともにアニエスも外に目を向けた。
そこに繰り広げられた光景――それに、アニエスは『ぎょっ』と目を奪われた。
窓の向こうで、『世界が割れていた』。
その光景はそうとしか表現のしようがない。
広がる光景は森の姿であったが、斜に『ひび』のような『線』が見えた。
アニエスは目を擦ったが、光景は変わらなかった。
上から下まで、それこそ天の果てから大地に至るまで、すっかり引き通された1本の『線』。
それは揺らぎ、たわみ、その向こうにぎらぎらとした目を刺すような『かがやき』が満ちていた。
 匿川 名 2024-09-01 10:16
匿川 名 2024-09-01 10:16
古びた木の扉が内側へと開かれる。
きぃと軽く、老婆の笑み声のように響く乾いた音は、そのまま扉の年季を物語るかのようだった。
勇者はその中にのしと足を踏み入れる。
アニエスはそのあとにそろりと続いた。
――なんだろう、この感覚。
肌に感じるその思い。
言葉にし難い、どこか浮遊感にも似たような違和感がある。
夢の中で『自分は今夢の中に居る』と悟るときのような。
そこは居間であって、テーブルの上には冷めたのか湯気の立たない茶の入った白いカップが置かれていた。
その向こうには安楽椅子に座る老婆の姿があり、アニエスは瞬間ぎくりと固まった。
――その老婆は、こちらを見ていた。
――いや、正しくは『アニエスを観ていた』。
決して邪悪何かを感じるわけではなく、その眼差しは落ち着き、優しげでありながらも、どこか諦念のようなものを帯び、そして千里先での物事までもすっかり見透かすような『途方も無さ』を感じさせるものだった。
 匿川 名 2024-05-19 09:44
匿川 名 2024-05-19 09:44
じゃり、と音を立てて踏みしだかれた土は、砕けてブーツの下で薄く広がった。
揺れる大知の直中(ただなか)で、『その者』の眼前には倒れ微動だにしない少女の姿がふたつ。
――かたや、その胸の真中から血を滴らせ、かたや、その頭蓋に斜に開いた穴を設け。
いずれにしても、其処にはもう生命(いのち)と呼べる輝きの気配を感じることは適わず――。
男はふたつの屍(かばね)を見下ろす。
然してその眼差しは、まるで肉屋が肉の値踏みをするかの如く冷たく、およそ慈悲といった優しげな何かからは果てなく離れたところで立ち尽すかの如く。
しかし、
――全身に闇夜のように黒いローブを纏うその男の目が、不意に細まった。
そして胸に穴の開いた少女の傍らで膝をついた。
男は自らの顔をその少女の顔に近づけた。
まるで読みがたい何かを確かめようとするかのように。
男の目が少女の閉じた瞼の側に寄る。
その差、僅かに一寸といったところか。
すると、男の見つめる眼差しの先で、
少女の瞼が極めて微かに、ぴくり、ぴくりと蠢いた。
――それは閉じた瞼の後ろで瞳が動いていることの証。
男は少し驚いたかの如く、目を見開きつつ、すいと頭を後ろに仰け反らせた。
そして『ふむ』とひとりごちると、倒れるふたりの少女の姿を今一度眺め見た。
一度頷き、男は何かを決めたようだった。
そしてしゃがみ込み、少女らの身体を器用にひとりずつその両肩に乗せていった。
『ハイヤ』と男が鋭く声を上げた。
すると大地をなぞるかの如く、鋭く早く黒い影が疾駆し、男の前に伏せた。
それは――巨大な黒犬だった。
大人の男ならひと呑みで喰らってしまいそうな、身の丈ならむしろ二頭の馬を並べた姿に近いような。
しかしその黒犬は男の前で、無限の忠義を示すが如く静かに待った。
男はその背に少女らの身体を乗せ、ローブの下で腰に備えていた縄を使って器用に結わえ付けた。
それから、自らも黒犬のその上に跨がった。
全てが整うと、男は声を発するわけでもなく、ただ顎を前にしゃくった。
黒犬は背に居る男の姿が見えるかの如く、それに倣って立ち上がり、軽やかに歩み始めた。
 匿川 名 2024-05-02 16:15
匿川 名 2024-05-02 16:15
わあ、すごい!
気がつけば月イチ連載だ!
次はもう少し早めに書きます。
・・・多分(滝汗
繰り返しますが、ここ数年ひとりで書いてますけど本作への乱入は全然OKですよ?
何しろ元々私も乱入者側ですので・・・。
大真面目でも、ふざけてても。
気が向いた方、どうかよろしくお願いします。
ほらほら・・・ね?怖くないってば☆
 匿川 名 2024-05-02 16:08
匿川 名 2024-05-02 16:08
歩みにつれて深くなる木々が紡ぐ影は、時々そこが大地の上であるにも関わらず、恰(あたか)も洞の中へと続くような錯覚を侍に抱かせた。
ただ勇者の歩みに従い、それに連なるだけではあるが、まるで不安を感じないわけでは無い。
漠とした素性の知れないざわめきを心の奥に抱きつつ、しかしそれでも彼と彼女――侍の脇で歩みを連ねる女騎士――は、唯ひとつだけ分かっていることがあり、それは『征くしか無い』という行動に対する『選択肢の不存在』だった。
勇者は何処へ行こうとしているのか。
そして、何故に火口はこのような森林に姿を変えたのか。
まるで、そう。まるでそれは『魔法そのもの』であるかのように。
『闇』とはいうまい。
何しろ木々の切れ間は儚くとも木漏れ日を差し続けている。
そこを無言で歩き征くのは勇者で、
その後背に付き従うのが我々で、
起きた『現象』に対する説明の術すら持たず、
他に取り得べき手段も無い。
侍はそこで、ふと眼を細めた。
足下を見やる。
――大地がまた揺れている。
がさがさと音を立てて、葉の切れ間から大小の鳥が飛び立った。
それに眼を向けたとき――
――侍の目の前に、明かりが広がった。
否、そこには明るい『広場』があった。
つい今し方まで其処には森が、木々の障壁が広がっていたと思っていたのに。
その明るい広場の中へと勇者は歩みを向ける。
束の間ぼうと立ち尽くしていた自分に気がついた侍は、早足でそれをさらに追う。
女騎士は意外にも、勇者のあとを淡々と歩み追い続けていたので、侍は自分だけが呆気にとられていたのだと分かった。
森を抜け、広場に入ると、その奥にある小屋が目に付いた。
その小屋は大樹の根に沿って設けられ、一見して景色に溶け込んでいたが、紛れもなく人が建てた物であって、窓には綺麗に磨かれた硝子が填め込んであった。
 匿川 名 2024-04-08 23:35
匿川 名 2024-04-08 23:35
女騎士は――訝しんだ。
否、それは正しくない。
感触としては、奇想に囚われた奇術の観客のように、
寧ろ『途方に暮れた』と評するのが正しいのかもしれないが、
それでも眼前(めのまえ)に広がる光景には、
刮目したうえで、すうんと鼻から長い息を吐くほかに出来ることがなかった。
「これは・・・」
侍が細い声音で呟いた。
彼らの瞬く間に眺望(ながめ)は、変わり果てていた。
彼らの前には勇者の背がある。
そして辺りを囲むのは、
――一面を占める、緑の茂る森の姿であった。
ただ今し方まで其処に在った火口は無く、
熱気と暗く覆う噴煙も無い。
寧ろ穏やかでしか無い緑の香りが、
素っ頓狂なまでに場違いな印象で、
彼等の鼻腔をさらり、さらりとくすぐった。
侍と女騎士が互いの目を見合わせて、眉根を寄せ合う。
その前で、背を向ける勇者はひと言も発さず、つか、と前へと歩みを向けた。
恐る、といった様子で二人がそれに倣おうとしたとき、
世界が鷹揚に――また、その背を揺すり始めた。
瞬間、二人は理解した。
今居る処が何処で在れ、此処は『続く大地(たいち)、あるいは世界である』と。
そのうえで、此処が何処で在るのかは、実はそれほど大きな意味を持ち得ない。
何故ならそも、彼らは此処が何処で在れ、
『それを含めて全てを遍く救うべく』居るのでは――なかったか。
剣(つるぎ)は失われ、世界は瞬きの間にその姿を変え、
――だが彼らは其処に在るので在れば、
『為すべきことは変わらずひとつ』であるのであれば、
彼女は黙って先を行く勇者に倣って歩みを前へと向けた。
同じく侍も黙り歩みを合わせた。
図らず、彼らは同じように歩みを続けることになった。
勇者が世界の果て、
或いは滾(たぎ)る火口へと歩んだときと同じように、
同じままに、
恰も――それは子羊が羊飼いに導かれるような、素朴で無心な頼りの素振りと倣いに似て――。